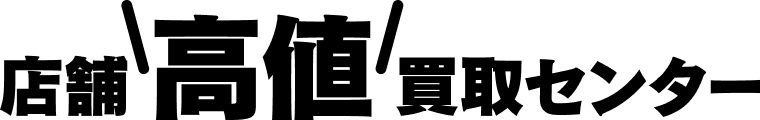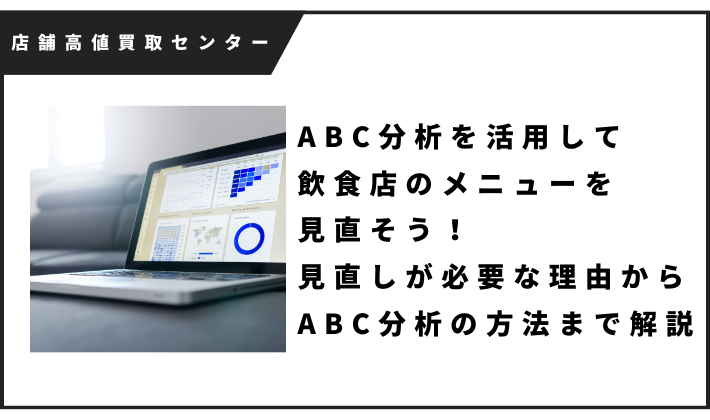
ABC分析を活用して飲食店のメニューを見直そう!見直しが必要な理由からABC分析の方法まで解説
今回は、飲食店のメニューをどのように見直したらいいのか、分析はどういった方法で行うのか、といった内容をご紹介していきます。
メニューの見直しが必要な理由
そもそもなぜメニューの見直しが必要なのかをまずは、説明していきます。
メニューは、売上や集客に大きな影響を与える存在であり、飲食店において重要な役割を担っており、メニューを見直したり分析したりすることは、繁盛店づくりにおいて必須です。
お客様の来店動機づくり
まず、飲食店における売上の6割に当たる部分は、2割のお得意様、または常連客で構成されています。お店の売上を成長させるためには、その2割のお客様に継続して来店してもらう必要があります。
そのためにも、メニューを常に見直し、季節ごとなどのある期間で新しいメニューを投入し、お店を飽きさせないようにしたり、新しいメニューを試そうという来店動機に繋げたりすることが重要です。
廃棄ロスの削減
メニューの見直しや分析によって、仕入れ量をどう調節すれば無駄のない商品管理ができるようになるのかを知ることが可能になります。
またメニューを絞ることで、ストックしておかなければならない食材の種類を減らすことが可能であり、廃棄ロスの削減に繋がります。
メニューを分析する方法
上記でメニューの見直しの重要性を説明しましたが、ここからは、メニューの見直しのための運勢方法について説明していきます。今回は、飲食店のメニューを分析したいという時によく用いられる、ABC分析について詳しく説明していきます。
ABC分析とは
そもそもABC分析とは、売上高や販売個数、粗利率などのある特定の指標からメニューをランク分けする分析のことです。これは、メニューの開発や在庫管理といった場面において、販売をするうえで優先するべきアイテムは何かを洗い出す方法です。
この分析を使うと、そのメニューが売上全体の中でどれほど貢献しているのか、影響力をひと目で把握することが可能になるとともに、お店で今売れている商品や、改善が必要なメニューが分かるため、対策も立てやすくなります。また、分析を使って現状を可視化することで、注力すべきメニューを確認し、増産やコストコントロール、在庫管理に生かすことができます。
ここからは具体的なABC分析の手順を説明していきます。
ステップ1. 調べたい商品の1か月の売上金額を算出する
まず、メニューひとつひとつの単価や販売個数、売上高のデータを用意し、メニューごとの単価と販売個数のデータが揃ったら、メニューごとの売上の金額を計算します。算出する際は、エクセルを使用するようにしましょう。
メニューごとの売上金額は、以下の数式で求められます。
メニューごとの売上金額=そのメニューの単価×メニューごとの販売数
その後、売上の構成比を以下の数式で算出します。
売上の構成比=メニューごとの売上金額÷全体の売上金額
ステップ2. 売上高の高い順にメニューを並べる
エクセルで、売上金額を「降順」にソートし、売上の金額が高い順に並べ替えます。
ステップ3. 売上累計と売上累積構成比を計算
売上累積構成比とは、その累計が売上の全体に対し、どのくらいの割合を占めているのかを表したもので、影響度が低くなるごとに数値は多くなります。
売上累計、売上累積構成比はそれぞれ、以下の式で求めることが可能です。
売上累計=そのメニューの売上高+当該メニューよりも上位のメニュー全ての売上高
売上累積構成比=売上累計÷全体の売上金額
この数値が次のステップで重要になります。
ステップ4. 売上累積構成比をもとにABCにランク分け
ABC分析では、パレートの法則というものを使用します。パレートの法則とは、「商品の売上高の8割は、全商品のうちの2割の品目が生み出す」という考え方です。
商品の売上高によって、「A」「B」「C」のランクに分け、売上に大きく貢献している商品、または売上にあまり貢献していない商品を可視化することができます。
Aグループ:累積売上割合が70%までの商品
Bグループ:累積売上割合が70%~90%の商品
Cグループ:累積売上割合が90%~100%の商品
上記のように分類し、ランクによって分けていきます。
ABC分析の活用方法
ここからは分析結果を具体的にどのように活用していけばいいのかを説明します。
Aグループの商品
総売上への貢献度が大きい商品、いわゆる「売れ筋商品」であり、更なる売上向上のために、メニューの中で大きく目立たせ、存在感を出すようにしましょう。
また、Aグループは中枢となるメニューなため、販売する個数を増やすと良いです。在庫管理では十分な保管場所を確保し、品切れが起きることのないように発注を行うことも重要です。またスタッフが接客時に積極的に薦めたり、その商品のPOPを店内の目につきやすいところに飾るなど、大々的に宣伝していくことがオススメです。
Bグループの商品
Aグループまでには及びませんが、それなりに売上を出している商品であり、適切に販売管理を行ったり、定期的に、もしくは在庫切れを見計らって発注を行うようにしましょう。販売個数が多いのであれば、在庫管理をしっかり行い原価率を下げるようにしましょう。原価率を下げることで利益率が上がり、Aグループに昇格する可能性もあります。
また、Aグループ商品と関連性の高いBグループ商品を、メニューの同じページに記載することで、売り上げ増加を狙うのも一つの手です。このような工夫により、Bグループの商品をAグループへと押し上げるようにしましょう。
Cグループの商品
Cグループの商品は、売上の貢献度が低い商品であり、「死筋商品」とも呼ばれる商品です。場合によってはメニューから外し、新しいメニューに入れ替えることも検討しましょう。しかし、やみくもに、メニューから外すのではなく、その際には、「メニューからなくした場合、不都合があるか」をよく考えてからメニューを消すようにしましょう。常連さんが確実に頼むメニューであれば、メニューからの削除はやめておいた方が良いかもしれません。
またメニューの入れ替えまではいかないという場合には、クーポンの配布などといった施策を考え、実行していくことが重要です。
今回は、メニューの見直し、分析方法について紹介しました。飲食店にとって、メニューの改善は売上の向上に直結する重要なことです。定期的にABC分析を行い、繁盛店を目指していきましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/