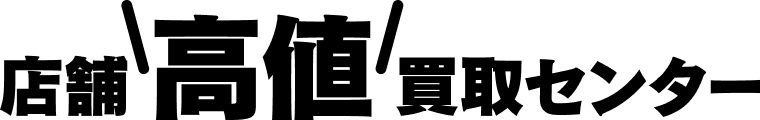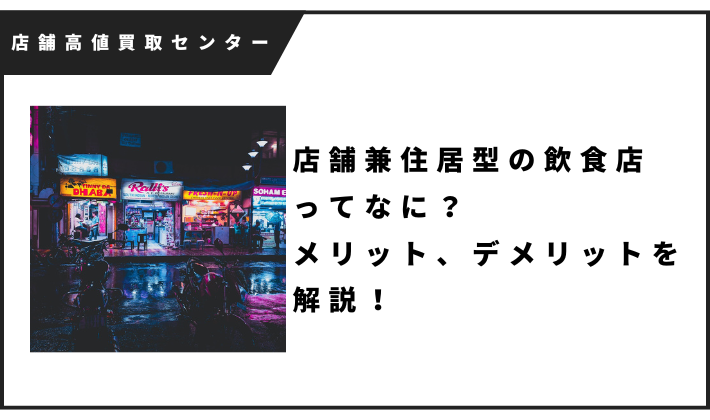
店舗兼住居型の飲食店ってなに?メリット、デメリットを解説!
飲食店経営を考えるのであれば、店舗として借りた場所に住みたいと一度は考える「店舗兼住居」。店舗兼住居の場合、家賃を抑えることが可能で、出勤時間を短縮することができ、時間も効率的に使うことが可能です。しかし、どんな物件でも店舗兼住宅にできるわけではないため、今回は店舗兼住居について解説していきます。
店舗兼住宅とは
一般的に店舗兼住宅とは、店舗と住宅の行き来ができる建物のことであり、建築基準法上では、店舗と住宅の行き来を建物内でできる建物を「兼用住宅」と呼び、建物内で行き来が出来ない建物を「併用住宅」と呼びます。店舗兼住宅として賃貸に出されている店舗は、店舗と住宅と両方で使用することを前提としているため、居住することに対して問題はありません。
次に店舗兼住宅のメリット、デメリットをそれぞれ紹介していきます。
メリット
まずメリットは以下の通りです。
・家賃を抑えることが可能
・通勤時間が短縮される
・家族経営の場合、育児や介護との両立がしやすい
デメリット
次にデメリットは以下の通りです。
・飲食店との兼用場合、匂い、害虫だけでなく騒音の問題が発生しやすい
・住宅に重きを置いた場合、集客が難しいことがある
・オンオフをつけることが難しくなる
店舗兼住宅に住む際の注意点
家賃に消費税がかかる
家賃の消費税は、居住用は非課税・事業用は課税がルールであり、店舗兼住宅の場合、店舗部分は課税で、居住部分は非課税の対象です。
契約書により、事業用と居住用とで家賃が分けられている場合、それに従うことが可能ですが、定められていない場合、店舗と居住用を区分する方法のひとつに「面積の比」があります。
例えば、家賃20万円で、店舗部分が40%、居住部分が60%の場合、家賃20万円のうち8万円が消費税の課税対象で、消費税率10%の場合、消費税8,000円が課税されます。
住民票を移す必要がある
住民票に記載されている住所は原則として現住所である必要があります。引越しする場合、「住民票の異動」が必要であり、正当な理由なく手続きをしなかった場合、罰則の対象となります。店舗兼住宅は居住を前提としている物件であるため、現住所として登録する必要があり、住むと決めた場合、住民票を移しましょう。
用途地域について
これから店舗兼住宅を探す場合、「用途地域」を確認するようにしましょう。これは、地域を整備したり発展させたりする目的で、13の地域に分けて地域ごとの建築制限が法律で定められています。
このうち「第一種低層住居専用地域」に最も厳しい制限があり、店舗兼住宅では、店舗床面積が50平方メートル以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもののみ飲食店を開業が可能です。また、これは「兼用住宅」に限られ、「併用住宅」では飲食店を出店、開業することはできないため注意が必要です。
用途地域については、以下に詳しく記載していますので確認してみてください。
また注意したいのが「定期借家物件」です。定期借家物件は、賃貸借契約期間満了後、原則として契約の更新ができないため、店舗と住まい、両方を探し直すことになるため注意が必要です。店舗兼住宅には、一般的な物件と違い、法的にもさまざまなルールが適用されるため、特徴を理解した上で、物件を判断するようにしましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/