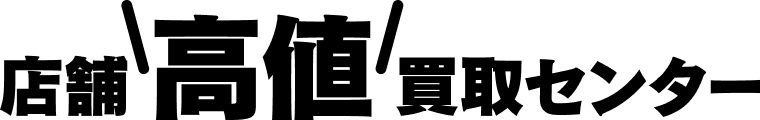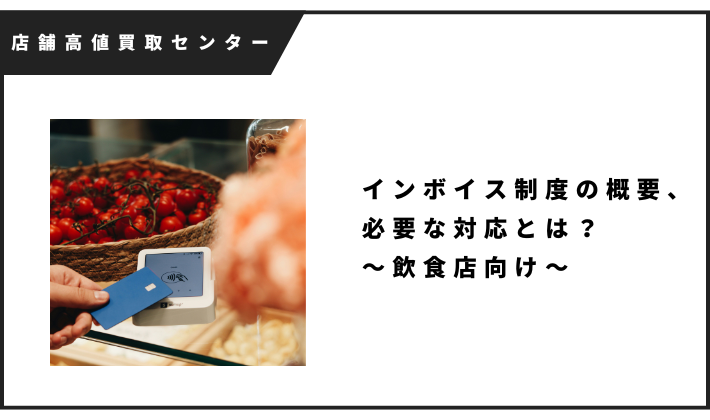
インボイス制度の概要、必要な対応とは?~飲食店向け~
インボイス制度の導入により、飲食店ではどのような対応が必要かについてお伝えします。インボイス制度では、売り手と買い手の双方に影響が及びます。売り手側では「売上の減少」や「お客様が離れる」リスクがあり、買い手側では「接待のしづらさ」が懸念されます。したがって、制度の概要を把握し、店舗経営への影響を適切に対処することが重要です。
この記事では、飲食店事業者が知っておくべきインボイス制度の概要や具体的な対応方法をわかりやすくまとめています。ケース別のルールも紹介しており、現在の店舗運営に問題がないか、改善が必要かを確認することができます。
1. インボイス制度とは
インボイス制度とは、仕入税額控除の方式として導入された「適格請求書保存方式」のことです。この制度により、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要となります。2023年10月1日から開始され、売り手側と買い手側の双方に影響を与える重要な制度です。
1-1 仕入税額控除の仕組み
インボイス制度により、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算することが可能になります。この仕組みは、消費税の二重課税を防ぐ役割を果たしています。仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の交付と保存が必須です。
1-2 インボイス制度の変更点
この制度は、売り手と買い手の両方に影響を与えます。消費税の課税事業者である買い手は、仕入税額控除を受けるために、売り手から適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。一方、売り手側は、買い手の要望に応じてインボイスを発行する義務があります。
また、インボイスを発行するには登録番号が必要です。登録番号を取得するためには、消費税の課税事業者である必要があり、免税事業者であってもインボイスを発行するためには課税事業者になる必要があります。
押さえておくべきポイント
- 仕入税額控除:課税事業者は仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要です。
- 登録番号の取得:インボイスを発行するためには、消費税の課税事業者として登録番号を取得する必要があります。
この2つが、インボイス制度で大きく変わる点です。
2. 飲食店がインボイス制度へ登録する場合のメリット・デメリット
インボイス制度への登録は、飲食店にもさまざまな影響を与えます。ここでは、飲食店がインボイス制度に登録するメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。
2-1 インボイス制度へ登録するメリット
飲食店がインボイス制度へ登録するメリットは、特に法人や接待客の維持に関係します。
- 法人客の利用維持:
法人や接待客が仕入税額控除を受けるためには、インボイスを発行できる店舗を利用する必要があります。インボイス制度へ登録することで、こうした法人利用の顧客を失わずに済み、売上の減少を防ぐことができます。 - 売上への影響を抑える:
接待やビジネスでの利用が多い飲食店にとっては、インボイス制度に対応することで売上への影響を最小限に抑えることができるため、制度登録は有利に働きます。
2-2 インボイス制度へ登録するデメリット
一方で、インボイス制度へ登録するデメリットもいくつかあります。
- 消費税の納税義務:
これまで免税事業者であった飲食店がインボイス制度へ登録すると、消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。これにより、消費税の支払い負担が増えるだけでなく、記帳や納税に関する事務作業が煩雑になる可能性があります。 - フォーム変更やシステム導入費用:
インボイス発行には、領収書やレシートに登録番号を記載する必要があるため、これらのフォーム変更が必要です。また、レジやシステムのインボイス対応のための導入費用もかかります。 - 告知費用:
インボイス対応店であることを明示するため、店頭やレジにポスターやステッカーを貼るといった告知が必要になる場合があります。これには、印刷費などのコストが発生します。 - 仕入先の対応リスク:
インボイス制度に対応していない仕入先からは適格請求書が発行されないため、その場合には仕入税額控除が受けられなくなります。これにより、仕入先との関係を見直す必要が出てくる可能性もあります。
2-3 インボイス制度への登録の重要性
インボイス制度への登録はデメリットもありますが、特に法人客やビジネス利用の多い飲食店にとっては、売上維持のために非常に重要です。法人利用が多い飲食店にとって、適格請求書を発行できるかどうかが接待や会議後の食事などに選ばれるかの大きなポイントになるため、登録しておくことが望ましいでしょう。
このように、インボイス制度へ登録することで得られるメリットと、デメリットによるコストや負担をしっかり考慮して、経営判断を行うことが大切です。
3. 飲食店においてインボイス制度が重要な理由
飲食店におけるインボイス制度の重要性について詳しく解説します。
3-1 インボイスが発行できないと利用者が減るリスク
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)が発行できない飲食店は、利用者にとって不利な選択肢となるリスクがあります。特に、法人客や接待利用の多い飲食店では、この影響が大きくなる可能性があります。
法人や課税事業者であるお客様は、接待などで支払った消費税を仕入税額控除として差し引くことができますが、それにはインボイスの提出が必要です。そのため、インボイスが発行できない飲食店での利用は控える傾向が強まり、顧客が減少する可能性があるのです。
さらに、インボイス制度の導入により、以前は消費税の免税事業者だった企業や事業主も課税事業者となるケースが増えています。これにより、インボイスが発行できない飲食店の影響はさらに大きくなることが予想されます。
3-2 インボイス制度への対応が飲食店選びの基準に
インボイス制度が導入されて以降、適格請求書を発行できるかどうかが、飲食店選びの基準の一つとなっています。特にビジネス利用や接待利用が多い飲食店では、インボイス対応の有無が予約時に確認されるケースが増えています。
飲食店は一般の個人客だけでなく、法人や事業主からも利用されるため、インボイス対応ができないと顧客の選択肢から外れる可能性が高まっています。そのため、インボイス制度に対応しているかどうかを明確に示すことが、集客や売上維持において重要です。
3-3 インボイス制度に対応していることを伝える方法
インボイス制度に対応していることを顧客にしっかり伝えることで、顧客の安心感を得られます。以下のような手段で、インボイス対応を積極的にアピールしましょう。
- 店頭やレジ前での告知:
店内に「インボイス対応しています」といったステッカーやポスターを掲示し、顧客が一目で分かるようにする。 - ウェブやSNSでのアピール:
店舗の公式サイトやSNS、グルメサイト、地図サービスなどに「インボイス対応」の記載を加え、インターネット上でも対応を知らせる。
このような対策を行うことで、法人客や事業者の安心感を高め、インボイス制度への対応が集客にもつながります。
4.【課税事業者、非課税事業者別】飲食店のインボイス制度対応の流れ
インボイス制度へ登録する際の流れについて、課税事業者の場合と非課税事業者の場合でそれぞれ解説します。
4-1 課税事業者の場合
すでに消費税の課税事業者である場合、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者の申請を行い、登録番号の取得が必要です。
手続きの流れ
- 申請書の提出:
国税庁のウェブサイトから適格請求書発行事業者の申請書をダウンロードして記入します。郵送でインボイス登録センターに送るか、e-taxを使ってオンライン申請することが可能です。個人事業者であれば、スマートフォンからも申請ができます。 - 登録番号の取得:
申請後、登録番号を取得するまでには、通常1~1.5ヵ月かかります。 - 準備作業:
登録番号を取得した後は、請求書やレシートのフォーム変更、レジや会計システムのインボイス対応設定などを行います。軽減税率対応も含め、これらの準備は早めに進めることが重要です。
4-2 非課税事業者の場合
非課税事業者がインボイス制度へ登録するには、まず消費税の課税事業者になる必要があります。これは免税事業者がインボイスを発行するための前提条件です。
手続きの流れ
- 課税事業者としての届出:
まず、税務署に対して「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となる手続きが必要です。この届出によって、消費税の納税義務が発生します。 - 適格請求書発行事業者の申請:
課税事業者として登録された後、適格請求書発行事業者の申請を行います。こちらも、申請は国税庁のサイトからダウンロードした書類を郵送するか、e-taxで申請できます。 - 登録番号の取得:
課税事業者と同様に、登録番号を取得するまでには1~1.5ヵ月かかります。 - システム対応と納税準備:
非課税事業者から課税事業者になることで、インボイスに対応するためのレジや会計システムの導入が必要となります。さらに、消費税を納めるための仕訳や帳簿の管理が必要になるため、事務負担が増える点にも注意が必要です。
課税事業者の場合、申請して登録番号を取得するだけでインボイス対応が可能ですが、非課税事業者は課税事業者への届出が必要となるため、より複雑な手続きが必要です。どちらの場合も、登録後のシステムや帳簿の対応が求められるため、早めの準備が推奨されます。
5. インボイス制度で活用したい制度やサービス
インボイス制度へ登録する際に、事業者が活用できる制度やサービスを以下に解説します。
5-1 負担軽減措置(2割特例)
2023年10月1日から2026年9月30日までの期間、小規模事業者がインボイス制度の登録に伴い課税事業者となる際の負担を軽減するための制度です。この特例を利用すると、登録後の最初の2年間は売上の8割を差し引いた金額で消費税額を計算できます。特に消費税納税に不慣れな小規模事業者にとって、負担を軽減する大きな助けとなるでしょう。
5-2 簡易課税制度
「簡易課税制度」は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象とし、実際の仕入額に基づかず、業種ごとのみなし仕入率を使って消費税額を簡便に計算できる制度です。利用するためには、事前に税務署への届出が必要です。飲食店の場合、業種区分ごとの利率を適用して、手間を軽減しながら消費税を納めることが可能です。
- 届出方法:e-taxでのオンライン申請か、国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードし、所轄の税務署へ提出します。
- 申請期限:適用を希望する課税期間初日の前日までに申請が必要です。
5-3 1万円未満の少額取引に関する措置
2023年10月1日から2029年9月30日までの期間、国内での課税仕入れについて、1万円未満の取引に関しては、インボイスがなくても帳簿保存で仕入税額控除を受けることができる特例措置が適用されます。この措置は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の売上高が5,000万円以下の事業者を対象としています。
さらに、1万円未満の値引きや割引に関しては、返還インボイスの発行が無期限で不要とされています。これにより、小額取引に対するインボイスの負担が軽減されます。
5-4 インボイス登録制度の見直し
2023年10月2日以降にインボイス制度へ登録する場合、申請書に登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録が可能です。これにより、事前準備を行う時間を確保しつつ、適切なタイミングでインボイス対応ができるようになっています。早めの申請が推奨されます。
5-5 事務コストを減らすための対策
インボイス制度の対応には、事務作業やシステム変更などのコストが増加することが予想されます。特に、アナログで行っていた業務のデジタル化(DX化)を進めることで、手間やコストを削減できます。
例えば、会計ソフトやインボイス対応のPOSシステムを導入することで、日常的な経理作業の効率が向上します。インボイス制度対応のタイミングを機に、業務全体を見直し、売上の維持や顧客体験の向上を図ることが、競争力を保つための一つの方法です。
まとめ
インボイス制度は、消費税課税事業者が仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の発行が必要となる制度です。飲食店においては、インボイス対応店になることで、法人や接待利用を確保し、売上の維持が期待できるメリットがあります。
インボイス制度に対応するためには、登録申請を行うことが必要です。また、レジや会計システムをインボイス対応にアップデートするなど、事前準備も重要です。特に、非課税事業者の場合は、インボイス制度への登録の是非を早めに検討し、対応を進めることが求められます。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP :https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/restaurantexit/
•出店希望者向け:https://t-kaitori.com/restaurantstart/