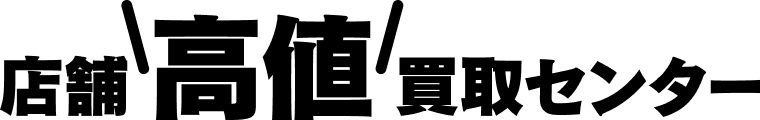飲食店におけるアレルギー対応:事例とヒューマンエラーを防ぐ方法
飲食店では、お客様の安全を守るためにアレルギー対応が重要です。しかし、ヒューマンエラーによるミスが発生することも避けられません。そこで、ヒューマンエラーに頼らない仕組みを取り入れることが効果的です。本記事では、事例とともにその具体的な方法を解説します。
事例:ヒューマンエラーが引き起こしたトラブル
事例1: 注文ミスによるアレルギー症状発生
あるカフェで、ナッツアレルギーのお客様が「ナッツなしで」と注文しました。しかし、厨房スタッフへの伝達が曖昧だったため、ナッツ入りのデザートが提供され、症状が発生しました。
• 原因:口頭での伝達に頼り、明確な仕組みがなかった。
事例2: メニュー情報の更新漏れ
新しいメニューが導入された際、アレルゲン情報が更新されておらず、お客様がアレルギー反応を起こしたケースです。
• 原因:メニュー管理が手作業で行われており、チェック体制が不十分だった。
ヒューマンエラーに頼らない仕組みの導入
1.デジタルシステムの活用
注文やアレルゲン情報をデジタル化することで、人的ミスを減らすことができます。
• POSシステム
アレルギー情報を登録し、注文時にアラートが出る仕組みを導入します。たとえば、「この料理には小麦が含まれています」といった警告が表示されるシステムです。
• メニュー管理ツール
クラウドベースのメニュー管理ツールを使用し、アレルゲン情報をリアルタイムで更新・共有します。これにより、誤情報の提供を防ぎます。
2.食材ラベルの徹底
仕入れ時に食材にアレルゲン情報が明記されたラベルを使用します。さらに、店内での保管時もラベルを活用し、調理スタッフが一目で確認できるようにします。
• カラーコードシステム
アレルゲンを含む食材を特定の色でラベル付けし、視覚的に区別します。
• QRコードの活用
ラベルにQRコードを追加し、スキャンすると詳細なアレルゲン情報が確認できる仕組みを導入します。
3.食材ラベルの徹底
コンタミネーション(異物混入)を防ぐため、調理環境を明確に分けることが必要です。
• 専用スペースの確保
アレルゲン対応食を調理する専用エリアを設け、通常の調理エリアと分離します。
• 専用調理器具の使用
アレルゲンを含む食品を調理する器具と、アレルギー対応用の器具を分けます。これらの器具には明確なラベルを付けます。
4.ワークフローの自動化
アレルギー対応が標準化されたワークフローに組み込まれていれば、個人の判断に依存しなくて済みます。
• チェックリストの導入
アレルギー対応の手順をチェックリスト化し、作業終了時に確認します。
• バーコードスキャン
提供する食品にバーコードを付け、注文内容と一致しているかスキャンで確認します。
事例:ヒューマンエラーを防いだ成功例
事例1: デジタルシステム導入によるミス防止
あるレストランでは、POSシステムを活用してお客様のアレルギー情報を注文時に入力。注文が厨房に届く際、自動的にアレルギー情報が表示される仕組みを取り入れました。結果、伝達ミスがゼロになり、安全な食事提供が可能になりました。
事例2: 厨房ゾーニングでコンタミ防止
洋菓子店では、アレルギー対応の焼き菓子を作る専用エリアを確保し、調理器具や作業台も完全に分けました。この取り組みにより、ナッツアレルギーのお客様からの信頼を得て、リピーターが増加しました。
まとめ
ヒューマンエラーはどの現場でも起こり得ますが、仕組みや環境を整えることで、リスクを大幅に減らすことができます。デジタルツールやラベル管理、作業区分化などを積極的に取り入れ、「ミスが起きにくい環境」を作ることが飲食店にとっての鍵です。
アレルギー対応はお客様の命を守るだけでなく、店舗の信頼を築くための重要な要素です。お店の運営に合った方法を取り入れ、安全で安心な食事体験を提供しましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP :https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け:
https://t-kaitori.com/restaurantexit/
•出店希望者向け:
https://t-kaitori.com/restaurantstart/
•居抜きビュッフェ-飲食店物件検索サービス
関東エリア:
https://app.t-kaitori.com/kanto
関西エリア:
https://app.t-kaitori.com/kansai