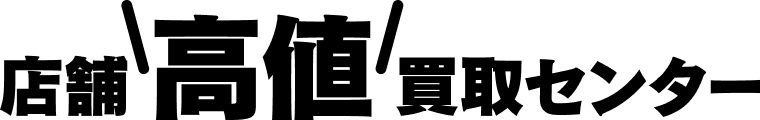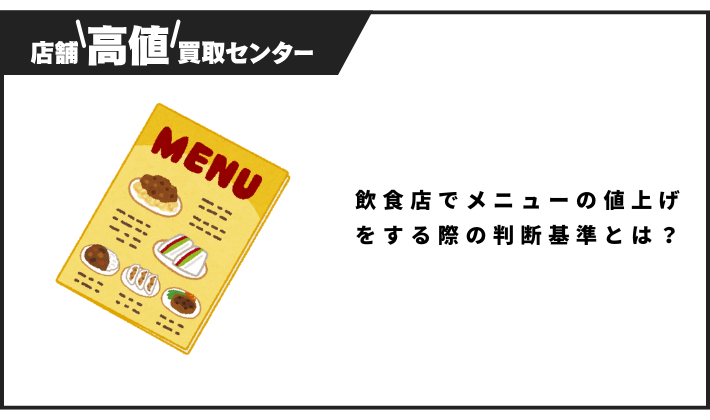
飲食店でメニューの値上げをする際の判断基準とは?
飲食店の運営では、原材料費や人件費の高騰、光熱費の上昇などの影響を受けて、メニューの価格見直しが必要になることがあります。しかし、値上げには慎重な判断が求められます。適切なタイミングと基準をもとに実施すれば、利益を確保しつつお客様の信頼を維持することが可能です。ここでは、値上げを検討する際の判断基準を具体的な数値や事例を元に解説します。
1.コスト構造の把握
まずは現状のコストを正確に把握しましょう。
• 原材料費
例えば、近年の食品価格高騰の影響で、2024年の食品原材料価格は前年比で約10〜15%増加したというデータがあります。
→ 判断基準: 原材料費が売上の30%を超える場合は値上げの検討を始めるサインと考えられます。
• 人件費
2024年には最低賃金が全国平均で4%上昇。人件費率が売上の25〜30%を超える場合、価格設定を再評価する必要があります。
• その他のコスト
光熱費や店舗維持費なども加味し、全体のコスト構造を明確化します。
→ 総コストが売上の70〜80%を占めるようであれば、値上げは避けられない状況といえます。
2.顧客定着度の分析
値上げが顧客離れを招かないかを判断するために、リピーターの割合や口コミ評価を分析します。
• リピーター率
常連客が全体の50%以上であれば、価格変更の影響を比較的抑えられる可能性があります。
• 事例: Aレストランでは、リピーター率が70%を超えることを確認後、全メニューを平均10%値上げ。結果、売上は12%増加し、常連客離れもほとんどありませんでした。
• 顧客アンケートの活用
値上げ前にアンケートを実施し、「価格」への意識を確認するのも効果的です。
→ 例: 「現在の価格に満足している」と回答した顧客が80%を超えた場合、値上げに対する反発は少ないと考えられます。
3.他店との比較
競合店舗の価格帯やサービス内容を調査し、自店舗のポジショニングを再確認します。
• 価格競争力の確認
同エリア内の同業種店舗の平均単価が1,200円で、自店舗が1,100円の場合、値上げによる競争力低下のリスクは低いと言えます。
• 事例
Bカフェでは、競合店が平均単価1,500円に対して、自店舗の価格は1,200円。これを1,350円に値上げしたところ、売上増加に成功しました。
4.メニュー戦略の見直し
値上げの影響を軽減するために、メニュー構成や提供サービスの付加価値を見直すのも有効です。
• 人気メニューの価格変更を慎重に
利益率の高い商品や注文数が多いメニューを中心に値上げを検討します。
例)高頻度で注文される「ランチセット」を50円値上げする一方で、目玉商品の「スペシャルデザート」は価格据え置き。
• セットメニューの活用
セットメニューを導入し、単品価格の値上げを目立たせないよう工夫します。
5.コミュニケーションの徹底
値上げを実施する際には、お客様に納得してもらうための説明が必要です。
• 店内ポスターやSNSの活用
「原材料の高騰」や「品質維持」のためであることを具体的に伝えます。
例文)「当店では地元産の新鮮な食材を使用し、品質を維持するために価格改定を行いました。これからも変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。」
• 値上げを機に特典を提供
値上げ後1週間の間に「次回使える割引クーポン」を配布するなど、顧客の満足度を高める施策を実施します。
まとめ
飲食店でメニューの値上げを行う際には、次のような基準を確認することが重要です。
- 原材料費や人件費の高騰など、コスト構造の把握
- リピーター率や顧客アンケートをもとにした顧客定着度の分析
- 競合店との価格帯比較
- 値上げに伴うメニュー戦略の見直し
- お客様への丁寧な説明と付加価値の提供
これらのポイントを踏まえた上で、慎重に値上げを進めることで、店舗の収益向上と顧客満足を両立させることができます。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP :https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け:
https://t-kaitori.com/restaurantexit/
•出店希望者向け:
https://t-kaitori.com/restaurantstart/
•居抜きビュッフェ-飲食店物件検索サービス
関東エリア:
https://app.t-kaitori.com/kanto
関西エリア:
https://app.t-kaitori.com/kansai