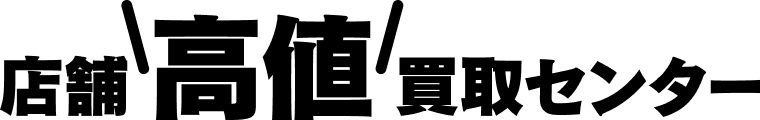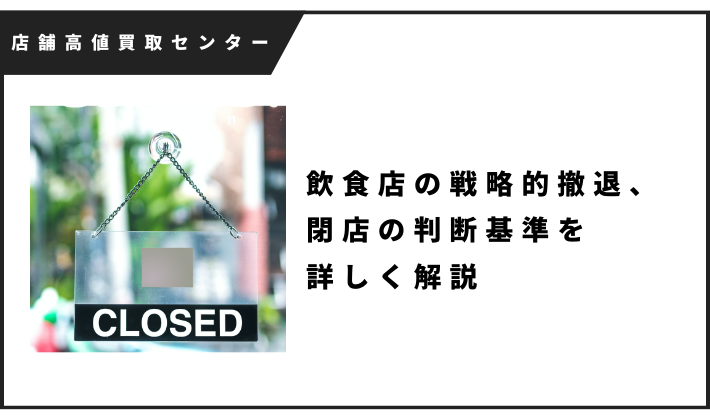
飲食店の戦略的撤退、閉店の判断基準を詳しく解説
客足減少による業績悪化など、飲食店オーナーは閉店という厳しい選択を迫られることがあります。閉店にもコストがかかるため、赤字経営になる前の戦略的撤退を視野に入れる必要があります。今回は、戦略的撤退の意味や、飲食店が閉店を決める判断基準を解説します。
そもそも「戦略的撤退」とは
そもそも戦略的撤退とは、将来的に経営の継続が難しいと判断した場合、閉店の際に発生するコストなどを考え、できるだけ有利な状態で撤退を進めることです。
飲食店は閉店を決めた後も、原状回復工事や厨房機器の売却などさまざまな手続きが必要になります。そのため、完全に資金が無くなってしまってから閉店するのでは、閉店にかかるコストを賄えません。長期的な視点を持ち、損失を極力抑えられるように計画性をもって閉店することが重要です。
閉店に陥る理由
次に飲食店が閉店に陥る理由について主な4つを解説していきます。
資金繰りが悪化する
資金繰りが悪化するということは、事業計画書通りに営業をすることができず予想以上にランニングコストがかかったり、集客が伸びないなどの要因が考えられます。
飲食店におけるランニングコストは具体的に、家賃、設備費、人件費、食材費です。安定して経営を続けるための、運転資金は最低でも6カ月分が必要といわれています。
環境、情勢の変化の影響
例えば、2020年に起こった、新型コロナウイルス感染拡大による営業時間の短縮要請や外出自粛は飲食業界に大きな影響を与えました。このような世界情勢に加え、材料費や光熱費の値上げも飲食店経営に影響を与えます。
トレンドの波が激しい
飲食業界は、流行やトレンドに合わせて開業、メニュー開発を行うことが多いです。しかし、流行は一過性のものであり、流行を受けた商品の売上の比重が大きい飲食店の場合は、トレンドに合わせメニュー変更もしくは業態転換する必要があります。対処が遅れた場合には、売上に大きな影響がでる可能性もあります。
人手不足と後継者不足
労働時間の長さや収入の低さによる、人材不足や後継者不足は深刻です。非正規の従業員を抱える店が多く、入れ替わりが激しいため定着率が低いのも課題の1つです。またベテラン従業員の仕事量が増えるだけでなく、十分に新人教育を行えないため、接客の品質低下にもつながり、売上が伸びない原因になります。また、経営者の高齢化も進み、事業継承ができず廃業に至るお店も多いです。
戦略的撤退の方法
戦略的撤退には複数の方法があります。それぞれの撤退方法を理解し、現状に合った撤退方法を検討しましょう。
事業譲渡
事業譲渡とは、現在のオーナーが経営を退き、第3者にオーナー事業を引き継ぐ方法です。経営権を無償で譲る場合と、事業に価値があるとされた場合、売却益などを残せる可能性があります。
事業譲渡は、経営からは手を引きたいが、お店の味や店舗を残したいという場合におすすめです。
資産売却
資産売却とは店舗で使用している厨房機器や椅子やテーブルなどの資産を他社へ売却することにより、金銭を確保することです。売却時には、業務機器を専門に取り扱う業者を利用します。
事業譲渡よりも早く撤退可能ですが、安値で売却価格を提示される場合もあり、多額の収益は見込めないことが多いです。
撤退
これは、事業や店舗を完全に終了し、店舗の撤退することを指します。借りていた店舗の、原状回復工事の実施、もしくは居抜き売却の手続きを行います。撤退する場合には、売却先の検討や原状回復工事が必要なため、さまざまな手続きを実施するため、撤退までにかかる時間やコストの負担も大きいことが多いです。また、手続き完了までは、賃料が発生することも想定しておきましょう。
通常では撤退までに時間がかかることが多いですが、弊社では、最短2週間で撤退することも可能ですので、一度是非ご相談ください。
戦略的撤退の判断ポイント3つ
戦略的について明確なガイドラインや基準はありません。そのため、経営者自らがルールを決め、その基準を下回るかどうか判断しなくてはなりません。例として事業撤退の判断基準になる3つのポイントを紹介します。
市場シェアや顧客を見極める
複数の事業や商品がある企業の場合、各事業や商品、メニューをどのタイミングで縮小、撤退をするのかを明確にする必要があります。今後の成長が見込める分野なのか、市場シェアや顧客の動向は今後どうなるのかなどを総合的に判断することが大切です。市場シェアの獲得が難しいと判断した場合や、成長が望めない分野の場合、撤退も視野に入れましょう。
事業が会社全体のどの程度の利益なのかを算出
営業を継続的に行う上で、利益は不可欠。営業利益では赤字であっても、貢献利益(売上高 – 変動費 – 直接固定費=貢献利益)が黒字であれば一般的に撤退するほどではないという考え方もあります。
しかし、必要な利益は企業により異なり、どの程度の利益を必要とするのかの基準は経営者が把握しておく必要があります。
事業を長期的にみる
現在の集客が少ない場合でも、店舗の位置する場所が開発地域に当たるような場所であれば、人の流れが大きく変わり今後集客を見込めるようになる可能性があります。また、事業が創業期、成長期の場合、その後の進展や黒字化が期待できることもあります。現状だけを見て判断するのではなく、長期的な見通しももつことが経営を続けていくことが重要です。
今回は戦略的撤退について解説しました。今現状は黒字であっても、今後経営が傾く可能性もあるため、万が一に備えて撤退基準を設けておくのも一つの手です。撤退を検討される場合は、まずは弊社にご相談ください。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/