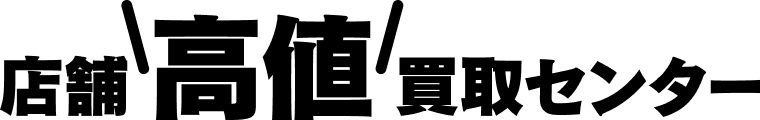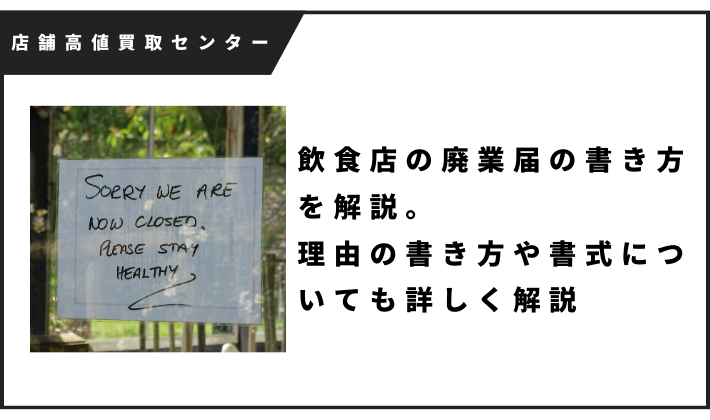
飲食店の廃業届の書き方を解説。理由の書き方や書式についても詳しく解説
飲食店を閉店する際に、廃業届が必要になります。いざ閉店するとなると、廃業届に記入する理由をどのように書くか悩む方もいるかと思いますので、今回は、廃業届の書き方や提出までの流れを解説します。廃業届以外に提出が必要な届出書もあわせてご紹介するため、閉店をお考えの方は今回の記事を参考にしてください。
廃業届とは
そもそも今回の記事のメインテーマである廃業届とは、個人事業主が行っている事業を終了するにあたり、税務署に提出しなければならない書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」であり、所得税法により提出が義務付けられています。
この届出書を提出することで、個人事業主として支払う税金の納付が不要になります。また「廃業届」は、保健所に提出する「廃業届」とは別の書類なので注意が必要です。また、廃業届を提出後、その旨を国や都道府県に報告する必要があります。
廃業届の提出先
廃業届は、開業している飲食店を管轄する税務署に提出する必要があります。
管轄する税務署については、開業届の控えを確認するか、国税庁のホームページでも調べましょう。
提出方法は、持参する、郵送、e-Taxによる電子申請から選ぶことが可能です。提出にあたっての手数料はかかりません。
また、持参して「廃業届」を提出する場合は、提出時に本人確認のため、「マイナンバーカード」1点、もしくは「マイナンバーを証明する書類」と「本人確認書類」(運転免許証等)の2点を持参しましょう。また郵送の場合は上記の書類のコピーを添付し、e-Tax申請の場合は本人確認は不要です。
廃業届を提出するタイミング
廃業届の提出は、廃業した日から1か月以内に提出する必要があります。提出期限が土日祝日にあたる場合、翌日が期限になります。廃業届は、提出日を記入する箇所があるので、提出日を確定して記入する必要があります。別枠に「廃業日」を記入する箇所がありますが、これは提出日とは別ですので注意しましょう。
廃業届の作成前に準備するもの
廃業届を書く際には、以下の3つをそろえて作成を始めましょう。
・廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の用紙
・マイナンバー
・開業届か確定申告書の控え
廃業届の用紙は、管轄の税務署もしくは国税庁のHP でダウンロードすることが可能です。また廃業届には、マイナンバーを記入する箇所があるため、マイナンバー通知書やマイナンバーカードなど、マイナンバーが確認できるものを手元に用意してから作成を開始しましょう。また、廃業届と開業届は同じ様式なので、記入する内容が重複している箇所が多くあるため、開業届の控えがあれば、確認する事項が減るため開業届の控えを用意していくことで負担が減ります。ここで、開業届の控えがない場合には、確定申告書の控えでも廃業届作成の負担を減らすことをできます。
廃業届の書き方
ここからは、何を記入するか詳しく解説します。
記入する際は、漏れのないよう届の最上段から書いていき、完成した後は必ず確認するようにしましょう。
1. 税務署名・提出日・納税地・上記以外の住所地、事業所・個人情報
まずは、廃業届を提出する税務署名、提出日など指示された項目を記入します。職業は、「飲食店業」と記入し、屋号もあれば記入するようにしましょう。開業届を記入したときと変更がなければ、提出日以外は、事前に用意しておいた開業届の控えを見て記入しましょう。納税地以外にも、住所地や事業所等がある場合はその所在地も記入する必要があります。例えば、自宅と店舗の場所が別で、店舗を納税地とする場合、自宅の住所を記入しましょう。
2. 届け出の区分
次に届け出の区分ですが、「廃業」にチェックを入れて、(事由)の部分に廃業する理由を記入します。理由については、以下を参考にしてください。
・「業績不振のため事業継続が困難である」
・「後継者不在により事業継続が困難である」
・「事業主の健康上の理由により事業継続が困難である」
上記に様に1行程度で簡潔に理由を記入するようにし、事業主が死亡したことが理由である場合は、「死亡」と記入します。また、事業譲渡する場合には、譲渡先の住所氏名を明記します。
3. 所得の種類と廃業日
所得の種類については、「事業所得」です。
「廃業の場合・・・」欄の「全部」か「一部」にチェックを入れ、「廃業日」を記入しましょう。ここで記入した廃業日から事業者としての納税が不要になります。また、同時に経費の計上も廃業日以降は認められません。そのため、廃業日の設定には注意しましょう。また、もし事業主が死亡して廃業する場合、死亡日が廃業日になります。
4. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
個人事業主の場合、ここの欄の記入は不要です。法人で上記に当てはまる場合、記入しましょう。
5. 廃業の事由が法人の設立に伴う場合
ここの欄は、通常の廃業であれば記入する必要はありません。また、個人事業主が法人になる場合は記入が必要です。
6. 開業、廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告書の取りやめ届出書」と「消費税に関する事業廃止届出書」を提出する場合は、それぞれ該当欄にチェックを入れましょう。
7. 事業の概要
事業内容に変更がなければ事前に用意した「開業届」の控えを見て同じ内容を転記しましょう。開業した時と提供する飲食物が変わったり、サービスを増やしたりした場合、現状の事業を記入しましょう。
8. 給与等の支払い状況
「給与等の支払い状況」についても、事前に用意した「開業届」の控えを見ながら同じ内容を転記すれば問題ないです。しかし、事業を長く続けていると変更していることも多いです。そのため、変更がある場合には、現状を記入する必要があります。特に、「従業員数」は変化していることが多いため注意が必要です。また、「給与支払を開始する年月日」は記入する必要はありません。
9. その他参考事項
他者に事業を譲渡した場合、給与等の支払事務を引き継いだ先の事務所等の所在地を記入しましょう。
10. 関与税理士
廃業届の作成を税理士に依頼した場合、税理士の情報をここに記入する必要があり、自分ですべて作成した場合は、記入不要です。
廃業届以外の税務署に提出する届出
廃業届以外にも、税務署に提出しなければならない届出書があります。またどの届出書にも提出期限があるため、事前に確認しておく必要があります。主な提出書類は、以下の通りなので確認してください。
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
・消費税の事業廃止届出書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
・個人事業主の死亡届出書(個人事業主の死亡が廃業の理由である場合に提出が必要)
事業の経営状況により、提出すべき書類は異なるため注意が必要です。提出すべき書類を提出しなかった場合、余分に税金を徴収されるなど不利益があるため、自身がどの届出を提出すべきなのかを税務署に確認する必要があります。また、税務署以外にも、保健所、日本年金機構、消防署、都道府県税事務所など関係各所に提出する書類があるため、それぞれの書類の提出先を間違えないように注意しましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/