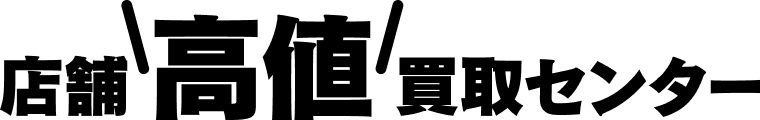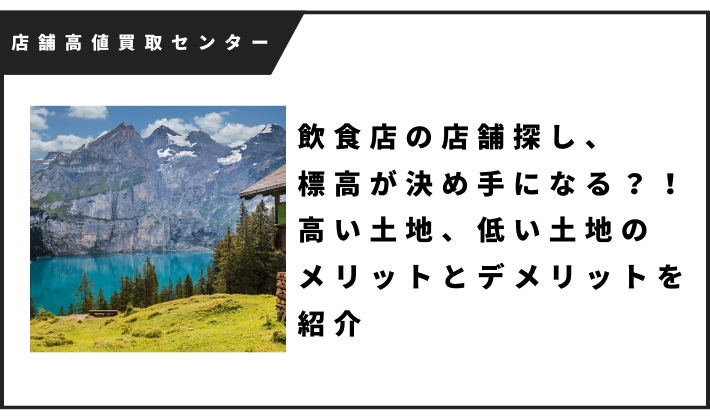
飲食店の店舗探し、標高が決め手になる?!高い土地、低い土地のメリットとデメリットを紹介
飲食店の出店において、標高の高い土地と低い土地をあまり気にしたことが無いかもしれませんが、それぞれどんなメリットやデメリットがあるのかを説明していきたいと思います。標高という新たな視点をもつことで、「穴場」のエリアと出合える可能性もあります。
「標高」と「海抜」とは
そもそも今回のテーマである「標高」とは、東京湾の平均海面を0mの基準面として、そこからの高さを測ったもののことを表します。一方で、「海抜」とは、その地域の近隣の海面からの高さのことを指し、例えば、大阪市であれば、大阪湾からの高さのことです。
また、実際に水面からの正確な高さを図るときに基準となるのが「水準点」で、これは、全国の主な道路沿いなどに約2kmごとで設置されています。この水準点が、その地域での高さ測量の基準になります。またこれらの「標高」「海抜」「水準点」は、すべて国土交通省国土地理院により定められています。
標高の高い土地のメリットデメリット
標高(海抜)の高い土地のそれぞれのメリットデメリットについては以下の通りです。
メリット
・眺望が良い
・風通しが良い
・家賃が比較的安い可能性がある
「夜景が見える」「気持ちいい風を感じられる」のように、眺望や自然を活かすコンセプトの店舗デザインにする場合、メリットになります。またテラス席を多めに設置するなどの工夫をすることで、集客力のアップを望むこともできます。その他、標高が高い場合、居住を目的とした場合の家賃は高くなる傾向にありますが、飲食店の場合は逆に安くなることもあるため、確認してみましょう。
デメリット
・ふらっと立ち寄りづらい
・住宅地の可能性が高い
特に店の標高が最寄り駅よりも高い場合、店に着くまでにお客様が歩き疲れてしまう場合があり、駅近くの飲食店にお客様を奪われてしまう可能性があります。その他、住宅街の場合は近隣に店が少なく、「ショッピング帰りにふらっと立ち寄る」というような機会に恵まれません。集客力を得るためには、わざわざ足を運びたくなるようなプレミアム感のあるブランディング、そしてSNSの活用をする必要があります。
標高の低い土地のメリットデメリット
続いて、標高の低い土地のメリットとデメリットについても紹介していきます。
メリット
・人通りや交通量が多い
・アクセスが良い
標高の低い土地は街の中心地であることも多く、商業施設や商店街があるなど、人通りや交通量が多いです。待ち合わせや買い物帰りなどに利用してもらいやすいので、集客という点では大きなメリットです。アクセスの良さも集客の面でメリットです。
デメリット
・水害のリスク
・資産価値が低くなる
河川や海の近くなどいわゆる「海抜0m地帯」のエリアでは、氾濫や液状化などの水害リスクを想定する必要があり、災害マニュアルを用意する、盛り土を準備するなどの対策が必要です。このようなリスクから、店の資産価値が低くなることもデメリットです。
上記でそれぞれのメリット、デメリットを説明しましたが、駅からの距離や築年数、階数だけでなく、標高でも家賃が変わることがあります。坪単価が高い駅に隣接する土地をあえて狙うのも戦略のひとつであり、家賃が抑えられるため単価を低く設定できるうえ、価格面で隣駅の店より優位に立てる可能性があります。自然災害という点ではデメリットが多い標高の低い物件も、徒歩での移動が楽になるというメリットもあり、一長一短です。
このように「標高」を物件選びの新たな目安として、新たな店のコンセプトを考えてみてはいかがでしょうか。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/