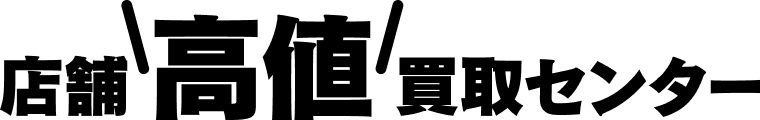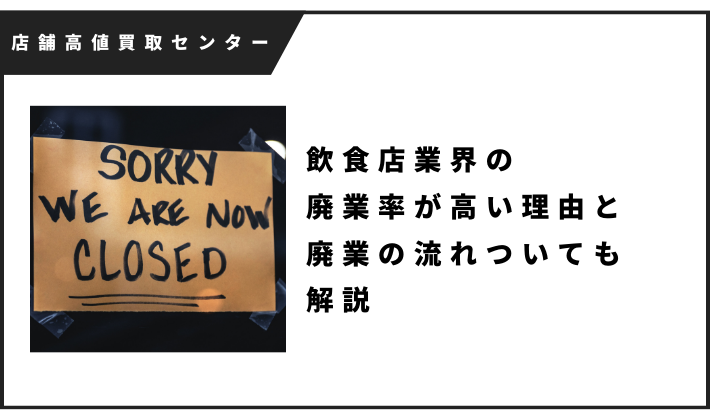
飲食店業界の廃業率が高い理由と廃業の流れついても解説
廃業率が高いといわれる飲食店業界。今回はなぜ飲食店の廃業率が高いといわれるのか、廃業の流れや今後の経営見通しなどについてご紹介します。
飲食店の廃業率
2022年中小企業庁の調査によると、飲食業の廃業率は5.6%で、すべての業種の中で最も廃業率の高い業界となっています。一方で、飲食業は開業率も17.0%と圧倒的に高く、これらのことから飲食業は入れ替わりが激しい業界といえます。一般的には、飲食店の1年以内の廃業率は30%、10年以内の廃業率は90%といわれています。その要因として、飲食店は流行の影響を大きく受けると共に、一言で飲食業と言っても業態が様々であることが挙げられます。また、異業種からの参入が多い業界でもあるため、比較的始めやすく、一度廃業しても別の業態で再チャレンジができる可能性もある業界です。
廃業率が高い理由
ここでは、飲食店の廃業率が高いといわれる4つの理由を説明します。
利益を出すことが難しい
一般的に飲食店の利益率は10%程度で、他業種に比べ低いです。また人件費と原材料費の比率が大きく、環境変化が利益に大きな影響を与えることも原因の1つです。今後もエネルギー高や、原材料費の高騰など、情勢をふまえた対策をしなければ利益を出すことが益々難しくなるでしょう。
多額の初期投資額
テナントの契約費や店内設備、厨房機器など、飲食店を開業するために、多額の初期投資額が必要です。また、開店から数年は、初期投資額の回収から始まります。初期の経営が不調な場合、返済に追われ黒字化が難しくなる可能性もあります。経営者にとって初期投資額をどのように抑えるかが、開店時の課題です。
運転資金の不足
飲食店を経営する上で、ランニングコストも必要です。ランニングコストとは、テナントとしての家賃、設備メンテナンス費、人件費、食材費などのことを指します。安定した収入がない場合、資金繰りが難しくなるため、開業前に綿密な事業計画を立て、実質利益と経費の計算など徹底した収支予測が必要です。
やり直しのコスト
飲食店は経営環境が変化し、それにあわせてリニューアルや業態変更をするという場合には、それなりのお金と時間が必要になります。余剰金がない場合、リニューアルや業態変更に踏み切れない恐れがあります。そのため、経営が厳しいまま続けていく場合も珍しくありません。
飲食店の廃業の流れ
飲食店の廃業が決まった場合の手続きの流れの一例は、以下の通りです。
1.不動産管理会社へ契約解除の連絡
2.従業員への解雇通知
3.取引先への連絡
4.行政へ各種届出
5.リース品の返却
6.保険の解約
7.電気・ガス・水道の解約
8.備品処分
テナントの場合、廃業が決まり次第、まず不動産管理会社への連絡を行い、その後、廃業の30日以上前を目安に、従業員への「解雇予告通知」を行います。解雇予告通知については、労働基準法で定められており、30日を切って通知すると不足の日数分の手当てを支払う義務が生じるため念頭に置いておきましょう。
解雇予告通知については、以下に詳しく記載していますので確認してみて下さい。
その他法人として手続きする場合と個人事業主として手続きする場合で、提出する書類が異なる場合があるため、必要な手続きをよく確認しましょう。
店舗を売却する場合はまず弊社にご相談ください。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/