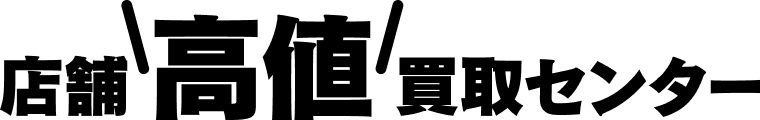飲食店開業準備のポイントと実際に開業するまでの流れや注意点を詳しく解説
飲食店経営が成功するかどうかは、開業準備にかかっているといっても過言ではありません。しかし、初めて飲食店の開業に挑戦する方の場合「飲食店を開業したいけど、どのように準備をしたらいいか分からない」といった悩みを抱えている方も多いと思います。今回は、飲食店の開業準備の基本や流れについて、分かりやすく解説します。
開業準備~開業するまでの流れ
開業準備から開業までを9つに分け説明していきます。
資金準備
まず飲食店を開業することに決めても、資金がなければどうにもなりません。飲食店を開業するには「物件取得費」「内外装工事費」「設備、家具、食器代」などが主に必要で、その総額はおよそ1000万円程度になることが多いです。
このうち最低でも1/3~1/2程度は自己資金でまかなう必要があります。そのためまずは、自己資金がどれくらいあるかを明確にするところから始めましょう。また、自己資金だけでは開業資金に足りない場合は「日本政策金融公庫」へ融資の相談をしてみるのがおすすめです。
立地とコンセプト
店のコンセプトが決まったら、出店予定地の客層やニーズとズレがないかを確認する必要があります。例えばファミリーがたくさん住んでいる住宅地に、ビジネスマン向けの居酒屋を開業しても集客を見込むことはできません。
店のコンセプトがその土地の客層やニーズにマッチしていれば、たとえ一等地でなくても集客を期待できる可能性もあります。そのため、あえて駅から離れた土地にしたり、住宅街の一角にしたりすることで、固定客を作り、安定した売り上げを目指す方法もあります。
物件探しから契約
開業する立地が決まれば、次は物件契約です。物件探しの段階では必ず複数の候補を用意し、絶対に実際に内見をしてから決めるようにしましょう。また、内見の際には店舗周辺の環境もしっかりと確認し、店のコンセプトに合っているかどうかを見極める必要があります。
物件の契約時に、保証金や礼金を支払いますが、保証金は家賃の3~10ヶ月分、礼金は1~2ヶ月分になることが多いです。その際の「物件取得費」は全て自己資金から支払う必要がありますので、覚えておいてください。
デザインから施工
物件の契約が終わったら、内外装のデザイン及び施工に進みます。ここで重要なのが、施工業者とは物件選びの段階から打ち合わせをしておくことです。これによりイメージしているデザインが実現可能かどうか、客観的な意見をもらえるためです。物件を契約してから、内装イメージを大幅に変更しなければならなかったり、追加料金が必要な施工になったりした場合、開業を断念しなくてはならないこともあります。飲食店施工実績の豊富な業者を選び、物件の下見に同行してもらうなど、しっかりとした関係を築いておくことが重要です。
食材業者選定
飲食店を開業するにあたって、食材業者の選定はとても大切なポイントです。早めにメニュー構成案を決め、必要な食材をリストアップしておくことをおススメします。肉、魚、野菜など、それぞれの専門業者に分け契約するのが一般的ですが、業者によって得意不得意があるため、同じカテゴリーで2社以上契約することをおすすすめします。
また複数業者に依頼すれば、常に比較検討しながら発注することが可能です。また業者を選定する際には、商品の質はもちろん、業者の評判、最小ロットや支払い方法、実際の対応が丁寧かどうかも加味する必要があります。
備品購入
個人で飲食店を開業する場合、家具やインテリア、食器、レジ、文具なども全て自分で選んで購入します。これらの備品購入は、少なくとも30万円程度はかかります。事前に購入する備品をリストアップし、予算内に納められるように工夫をしましょう。また内外装の工事中に購入手配をすませておくと、その後の搬入をスムーズに行うことが可能です。
スタッフの確保
オープンの1か月前には、スタッフを確保する必要があります。スタッフを採用するとトレーニングを行う必要があるため、営業開始前から人件費が発生することを覚えておきましょう。そういう意味で、飲食未経験者だけでなく、経験者も揃えておきたいところです。
一般的には売上に対する人件費率は30%といわれていますが、券売機やセルフオーダー制を採用することで、人件費率を20~30%に抑えることも可能です。
各種書類届出
飲食店を開業するために必要な資格として、まず「食品衛生責任者」があげられます。これは、6時間ほどの講習を受け、合格試験等もないため、問題なく取得できます。しかし、時期によっては講習予約が1~2カ月先まで埋まっていることがあるため、早めに取得するようにしましょう。
次に「飲食店営業許可」が必要になります。これは保健所に申請しますが、厨房設備、手洗い、換気扇など、店舗の設備面においてかなり細かい決まりがありますので注意が必要です。そのため、店舗の内装施工前に、必ず保健所へ相談に行きましょう。その他、税務署へは「開業届」を提出する必要があります。同時に「青色申告承認申請書」を提出すれば、最高65万円の控除を受けることが可能です。
オープンまで
オープンが迫ってきたら、ホームページやショップカードなどの準備を始めましょう。近年ではSNSによるアピールが非常に有効であるため、インスタグラムだけれなくフェイスブックやX(旧Twitter)なども活用してみるようにしましょう。その他、友人や取引先を招いてレセプションパーティを開くのもおすすめです。開業に向けてリハーサルになるだけでなく、メニューや接客について率直な意見をもらえます。
開業準備の注意点
ここまでは開業の流れを説明しましたがここからは注意点を説明します。
融資の返済
開業資金を「日本政策金融公庫」等で借入した場合、毎月の返済を事業計画に入れることを忘れないようにしましょう。しかし、個人で借入した場合、個人の収入から支払うことになります。借入金の返済期間は5~6年が相場です。しかし、融資担当者の話をよく聞き、内容をしっかりと理解したうえで決定するようにしましょう。
物件を取得しなければ融資申請できない
融資は、飲食店を開業するための物件を契約している証拠がなければ申請することができません。物件の契約書や領収書はもちろん、店舗デザインや施工の見積書、備品の概算見積もりに至るまで、細かく提出しなければなりません。店舗契約前に購入した備品の領収書なども残しておくようにしましょう。
以下に資金調達より先に物件選びをする必要がある旨の説明を詳しくしていますので、併せて読んでみて下さい。
家賃比率や運転資金などの計算
飲食店経営では、売上に対する家賃比率は10%前後が理想だといわれています。店舗候補の物件が見つかったら、まずは物件の家賃の10倍以上の売り上げが見込めるかどうかを試算しましょう。
もし、家賃が売り上げ見込みの15%以上になってしまう場合、メニューの見直しや、物件の見送りを検討する必要があります。また、営業が軌道に乗るまでの運転資金も、同じく家賃の10倍程度あると安心できます。
様々な準備項目がありますが、同時に進行することも多いため、ToDoリストなどを作り、表にまとめるなどして、一つ一つチェックしながら進めていくことがおすすめです。特に物件契約、融資申請の前後はリサーチや相談を十分に行い、慎重な判断をしましょう。最初の1店舗をトラブルなくオープンさせることが何より重要です。長く続く飲食店となるように、しっかりとした計画を練って、開業準備を進めていきましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/