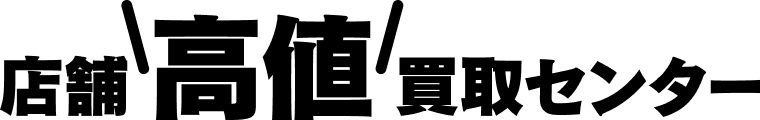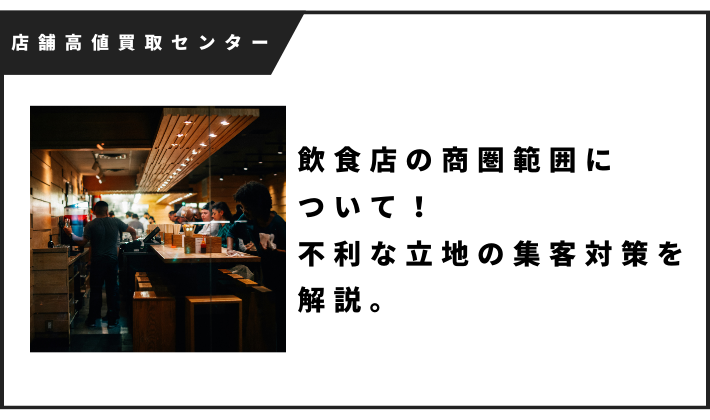
飲食店の商圏範囲について!不利な立地の集客対策を解説。
飲食店を経営していく中で、立地は非常に重要です。そのため「駅近」と言われる物件の人気は根強く、理想的な開業場所だと考える方は多いかと思います。しかし実際には、どんな業態・コンセプトであっても駅近が一等地とは限らず、「商圏範囲」が重要なこともあるため今回は、駅近の定義と商圏範囲の定め方と立地が悪くても飲食店を繁盛させるポイントについて解説していきます。
人気の駅近とは
駅近物件は、アクセスが良く、人通りが多いため集客につながる、広告費をかけずにプロモーションができるなど多くのメリットがあります。駅近には明確な定義はないですが、アンケート調査などの結果から多くの人は徒歩5分圏内を駅近ととらえていることが多いようです。また倍の徒歩10分にまで広げると、駅近と感じる人と感じない人が半々くらいに分かれるようです。これにより、駅近のお店かどうかは人ぞれぞれの感覚で評価されていることが分かります。
駅から徒歩5分圏内の物件は、家賃は一気に高くなり、競合も多いです。さらに、そもそも駅周辺の利用者と店の業態やコンセプトがマッチしていなければ、メリットを最大限に享受することができません。そのため、今回は駅近に限らず、商圏範囲についても解説していきます。
商圏範囲とは
そもそも「商圏範囲」とは、自店舗を利用する可能性が高い顧客が生活したり、働いたりしている範囲のことを指します。
例えば、都市部の場合、飲食店利用者は徒歩で移動することが多いため、商圏範囲は半径500メートル程度と言われています。また、不動産業界で用いられる「徒歩1分」は80メートルと定められており、これに従えば半径500メートルは5~10分で移動できる距離のことを指します。例えば回転数が求められるラーメンや丼ものの店舗なら、オフィスエリアから半径500メートル圏内の場所にあれば、ランチタイムにそのエリアからの集客が見込めそうです。
一方、で郊外の場合は車移動で飲食店に来店するため少し基準が違います。郊外の場合、車を利用して10分間で移動できる5キロメートル程度を商圏範囲とみなすことも可能です。しかし、幹線道路に近かったり、競合が少ない業態であれば、広範囲から目的を持って来店してもらえる可能性もあるため、1次商圏、2次商圏を定めてみるといいでしょう。
飲食店の立地の悪さをカバーする方法
上記について商圏についてお話しましたが、不利な立地に出店する場合、どうしたら良いかをここからは解説します。 一般的にマイナス要素になるのは、以下の通りです。
・人通りや交通量が少ない
・地下店舗や空中店舗である
・駐車場がない
・駐車場があっても駐車しづらい
このようなマイナス要素があっても、人気店になっている店舗は存在します。以下で対策について解説します。
リピーターを増やす
来てくれたお客さまにはファンになっていただき、リピーターを獲得しましょう。ここでしか食べられないようなメニューを考案し、定番メニューと期間限定メニューを用意することで、リピーターの増加を期待することができます。さらに店内やSNSで今後スタート予定の新メニューについての予告も発信し、「また来よう」と思える宣伝をしていきましょう。
視認性を上げる
見つかりづらい立地にある場合は、視認性を上げることが重要になります。看板の設置は必須ですが、現在はSNSの活用がより求められている時代です。視野性については以下に詳しく記載しているので、確認してみてください。
駐車場の確保
車移動が一般的な郊外地域の場合、駐車場があることはとても大切なポイントです。必要に応じ近くの土地を借りるか、近くのコインパーキングとの提携など、車で来店できる環境を整えるようにしましょう。駐車場についても以下に詳しく記載してますので、併せて読んでみてください。
物件選びをするうえで、立地は非常に重要であるのは確かですが、駅近でのみ店舗を探すのではなく自分の店のコンセプトにあった店舗を探してみるのはいかかでしょうか。商圏範囲の考えを取り入れたり、集客対策に力を入れるなどして、店舗づくりを進めてみてください。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/