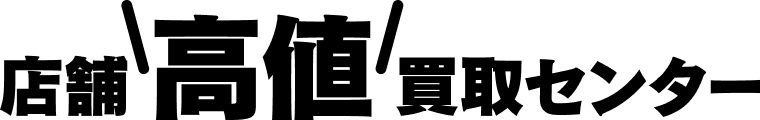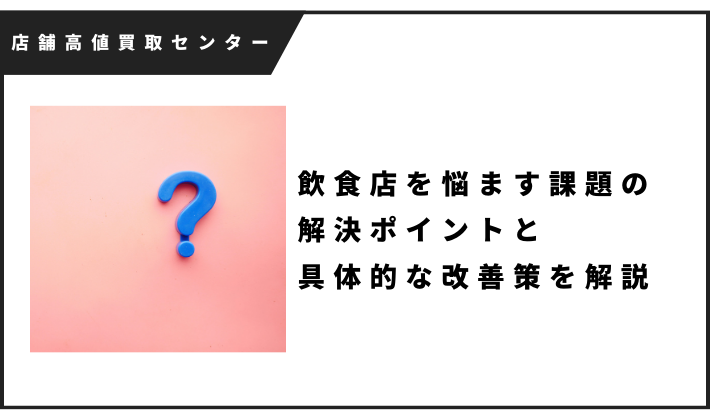
飲食店を悩ます課題の解決ポイントと具体的な改善策を解説
飲食店経営を行う際は課題が多く発生します。今回は、多くの飲食店が直面しやすい課題の正しい解決方法を紹介していきます。
飲食店を悩ます課題
利益が出にくい
飲食業は客単価が低く、利益率は10%程度と言われることが多いです。他の業種と比較し、利益を出しにくい傾向にあります。飲食店では、特に人件費と原材料費が大きな負担になり、昨今の円安や物価高の影響を大きく受けているかと思います。
また、新型コロナウイルスなど外的要因が、売上に大きく影響を与える点も利益が出しにくい理由のひとつです。そのため、自社だけで解決することが難しい事案も多く、頭を抱えるオーナーが多いです。
物価高騰による経費増加
原油価格が高騰し、電気代などの光熱費の値上げが飲食店経営に大きな影響を与えています。また、円安も重なり、物価や食材費・ガソリン代などの運送費も高騰、飲食店経営に、二重・三重の課題がのしかかっています。
また、1995年以降、消費者の賃金が上がらない状況が継続しており、消費者ニーズを考えると、物価が上がっても簡単に値上げに踏み切れない状況にあり、飲食店の経営を悩ます課題となっています。
人手不足
飲食業は、早朝、深夜の営業による長時間労働および収入が低いといったイメージが他の産業に比べて強い傾向にあります。そのため、ネガティブな印象から人手不足に陥りやすく、人材確保が課題です。
また、人件費の削減のために学生やアルバイト、派遣などの非正規雇用の従業員に頼らざる得ない状況で、定着率が悪いのも人手不足の原因のひとつです。イメージ改善には、業界全体としての取り組みも必要だと考えられます。
飲食店の課題解決のための5つのポイント
飲食店が抱える課題を上記で説明したので、これらを解決する5つのポイントを解説します。
顧客満足度
飲食店が安定的な収益を確保するためには、まずは「顧客満足度」を知ることが重要です。飲食店経営において重要な、顧客の満足度を図る指標「QSC」を徹底していきましょう。
例えば、飲食終了後などにアンケートを行い、顧客から意見を集めて、オペレーションの向上に役立てるようにしましょう。また、単にアンケートを依頼するだけでは高い回収率が望めないため、一品をサービスするなど回答に対するインセンティブを顧客に提供すると回収率を上げることができます。QSCについては以下に詳しく記載しているので、確認してみて下さい。
コストカット
飲食店のコストは、「Food(食材費)」「Labor(人件費)」「Rent(家賃)」のFLRで基本的に構成されており、売上の中でこれら3つの要素の割合 (FLR比率) が高くなるほど、資金繰りが悪化する原因になります。
FLR比率を計算し、コストカットできる部分がないか積極的に検討する必要があります。コスト削減には、カット野菜や調理済み食品、人件費の削減につながる商品を利用するのが有効です。FLRの比率の計算式は以下の通りです。
FLR比率(%)=(食材費+人件費+家賃)÷売上高×100
業務効率化
人手不足や経費の増加が課題となっている飲食業界では、初期導入費用がかかったとしても、業務のデジタル化や機械化を行う必要があります。例えば、タッチパネル注文や配膳ロボットの導入です。
その他、シフト管理や給与管理などのバックオフィス業務の負担、人員不足などによるオーダーミスなどにかかる手間も、デジタル化や機械化で解決できます。この分野は急速に発展が進んでいるため、常にアンテナを張り、最新の情報を取り入れてうまく活用しましょう。
人材確保と人材育成
従業員が集まる環境を作るために、人材育成環境の構築や制度を整えるようにしましょう。従業員の経験や個別性を考え、適切な業務量や待遇を用意することが重要です。人材不足は、接客の質の低下やスタッフの体調悪化、顧客離れなどに繋がります。一方で、従業員に対してよい環境を提供できれば、プラスのサイクルを生み出すことができるでしょう。
労働環境
飲食業界は他の業種と比べ、離職率が高いことで知られています。原因としては、上記の人材育成についてなどにも繋がりますが、労働時間の長さ、疲労が蓄積しても人員不足で休めないといった、劣悪な労働環境があるためです。
すぐに改善することが難しい場合でも、人間関係のトラブルは早期に解決する、労働条件を見直すなどできることから着手するようにしましょう。そうすることで、労働環境の改善につながり人材の定着率も上がっていきます。
5つのおすすめの改善策
ここでは環境を改善するおすすめの施策を5つ紹介します。
サービスの質の向上
売上を上げるためには、サービスの質を向上させることが重要です。既存顧客を飽きさせない新メニューの開発、客単価のアップにつながる施策を考えるようにしましょう。価格を設定する際には、単なる安売りでは利益を取ることはできません。食材の品質や店の雰囲気、サービスなどを考慮し、「価値に見合った価格」をつけることが重要になります。近年では価格だけでなく、品質を重要視する顧客層も増えています。
収支の把握
数字が苦手だからと避けるのではなく、飲食店経営者自らが帳簿の管理を行い、収入と支出の管理を行うようにしましょう。収支の把握が正しくできれば、不要なものやコストカットに繋がります。例えば、細かな工夫としては、箸や紙ナプキン等の消耗品は同業者やグループ店舗と共同で仕入れると、コストカットや仕入れの手間が省けます。
DXの導入
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を使ってビジネスモデルの構築や製品・サービスを変革すること指し、具体的に、QR決済などのキャッシュレへの対応やセルフレジ、タブレット注文の導入のことを指します。
また、ネット予約やWeb台帳など、デジタルツールの導入による業務効率化もDXのひとつであり、できるところからDX化を進めることでスタッフの業務負荷が減り、人件費の削減にもつながっていきます。
流行のニーズ調査
飲食業界のトレンドは移り変わりが激しいため、常に最新の情報を仕入れ、営業に活かすマーケティング力が重要になります。目の前の業務に追われるだけではなく、世の中の流行に常にアンテナを張っておかなくてはなりません。
また、SNSによる情報発信を通し、考えた施策や商品を世の中に伝えるPRも重要です。マーケティングやPRはすぐに力が身につくものではないため、軌道に乗るまでは専門の業者に力を借りるのも一つの手です。
業態の変更や店舗の移転
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言をきっかけに、テイクアウトやデリバリーのサービスを始めるなど、業態を変更する飲食店も増加しました。
また、オフィス街はテレワークの浸透により、人流が大きく変わるなどの現象が発生しました。環境が原因で集客できない場合は、店舗の場所を変えてみるのがよいです。その際には、お店のコンセプトやターゲット層に合う人を集客できる場所を選ぶことが重要になります。
飲食店を取り巻く課題と、解決方法について今回は、解説しました。飲食店にはさまざまな課題がありますが、DX推進などの工夫により改善施策が成功している企業も数多く見受けられますので、様々な工夫をして、良いお店作りを目指しましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/